こんにちは、行政書士のみどりです。
前回は「誰が後見人になるの?」というお話をしましたね。
今日はその続きとして、もう一つの制度、「任意後見制度」についてお話しします。
🐾 まねまる:
“任意”ってついてると、ちょっと柔らかい感じがするニャ。
「法定後見」とは何がちがうの?
💡 みどり:
いい質問だね、まねまる。
法定後見は、すでに判断能力が低下してしまったあとに、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。
それに対して、任意後見は、まだ判断能力がしっかりしているうちに、
「将来、自分が困ったときに助けてもらう人」を自分で決めておける制度なんだよ。
🐾 まねまる:
なるほどニャ〜! つまり、“今は元気だけど、将来のために契約しておく”ってことニャ?
💡 みどり:
そうなの。 たとえば「子どもが遠方にいる」「信頼できる人に将来お願いしたい」っていうとき、
あらかじめ公正証書で契約しておけば、
もし判断能力が落ちたときに、その人が正式に「任意後見人」としてサポートしてくれるんだ。
🐾 まねまる:
へぇ〜、自分で“将来の味方”を選べるんだニャ!
でも、その契約ってすぐに使えるの?
💡 みどり:
そこがポイント。 任意後見契約は、すぐには効力が発生しないの。
実際に判断能力が低下して、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点で、初めてスタートするの。
つまり、“契約だけ先にしておいて、必要になったら発動”という仕組みなんだ。
🐾 まねまる:
ふむふむ…。 じゃあ、今のうちに備えておけば、「いざというとき」にスムーズに動けるニャね。
💡 みどり:
そう。 実際、私たち行政書士にも「親の将来を考えて準備しておきたい」という相談が増えているよ。
判断力が落ちてからだと、もう契約ができないからね。
🐾 まねまる:
制度って、難しそうに見えて「安心のための選択肢」なんだニャ🐾
💡 みどり:
まさにそう。 成年後見制度にはいろんな形があるけれど、 共通しているのは「その人らしく生きるために支える」ということ。
次回は、制度を考えるときに大切なことについてお話ししますね。
任意後見は、「もしも」の前にできる大切な準備です。
元気な今だからこそ、考えてみる価値があります。
行政書士事務所&W(みどり&まねまる)



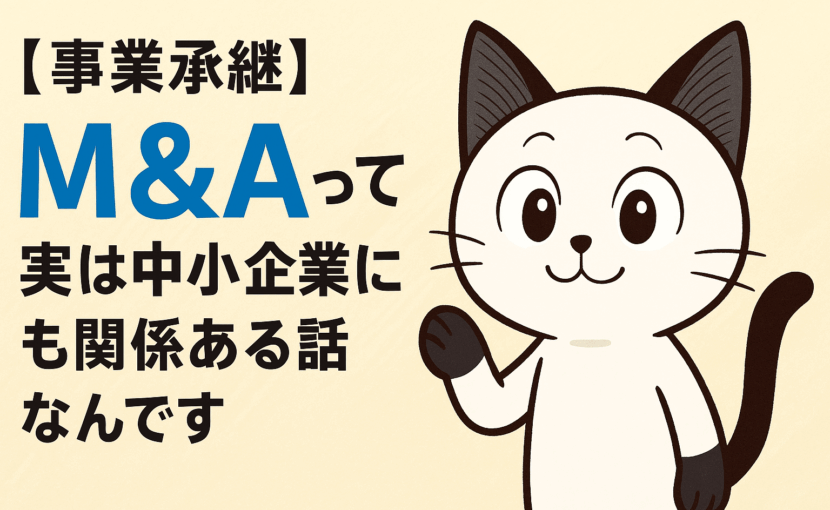



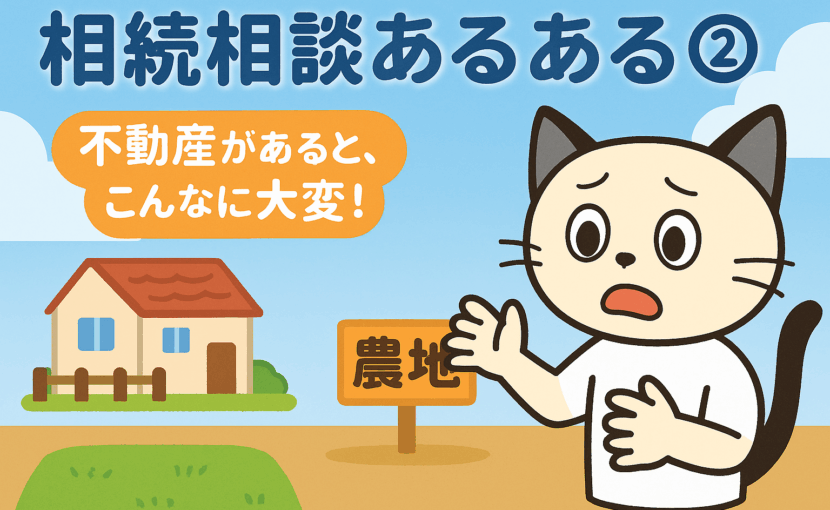



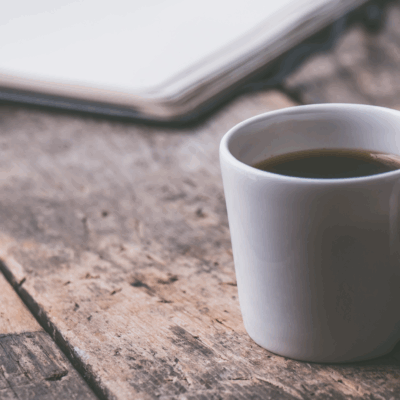

この記事へのコメントはありません。